2025/02/21
パート・アルバイトの通勤手当はいくら? 通勤手当の考え方
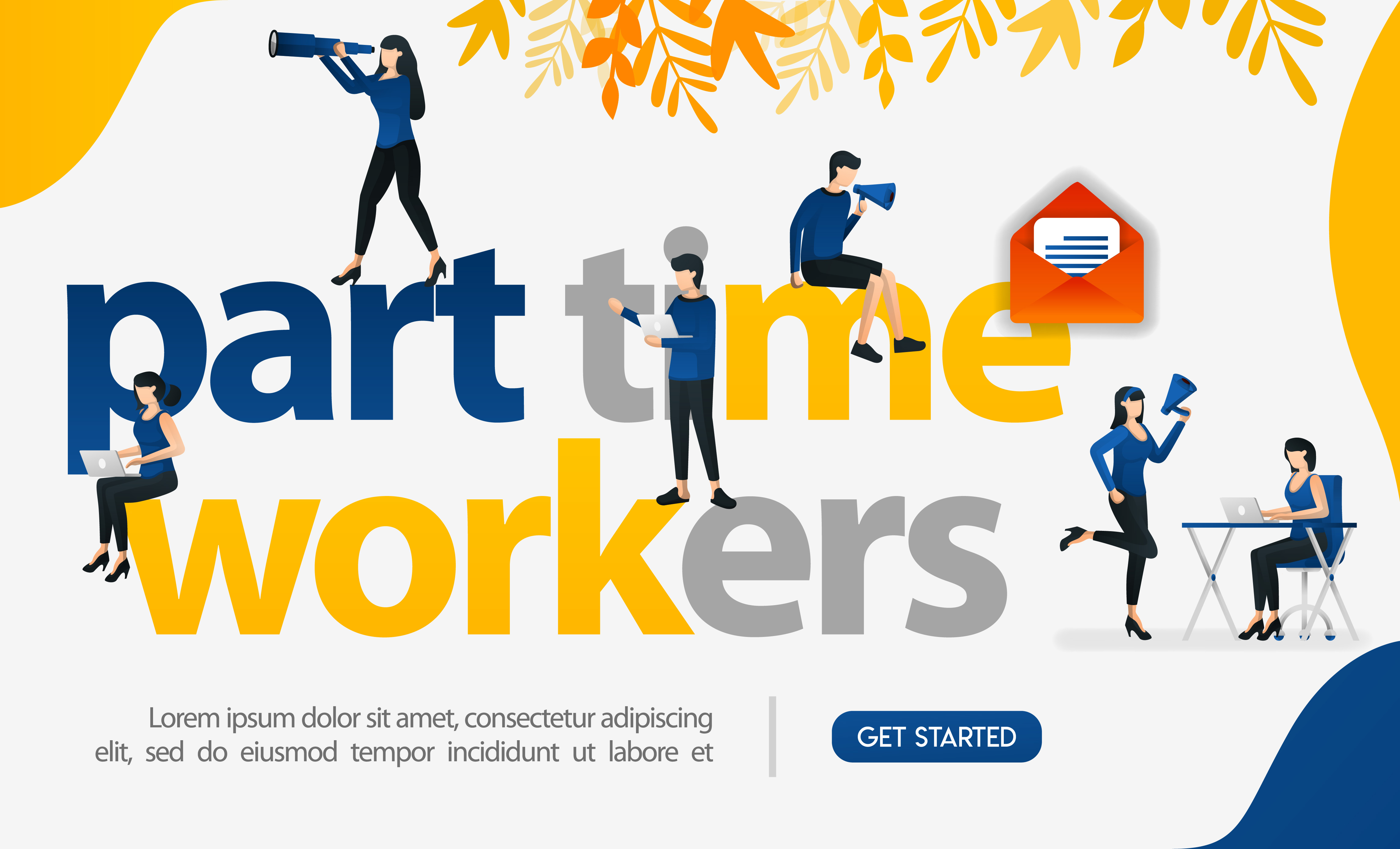
働き方は正社員のほかパートタイムやアルバイトなど多様です。通勤手当は、多くの人にとって勤務先を選ぶ際の指標となっています。多様な働き方に対応するため、人事・労務の業務担当者の方は、職制の違いによる通勤手当の支給ルールが異なることで通勤管理業務が煩雑となっている場合がみられます。
その中でも、パートタイムやアルバイト社員への通勤手当の支給の扱いについてどう扱えばよいのか、判断に迷う場合があるかもしれません。
当記事では、パートタイム社員、アルバイト社員への通勤手当支給の考え方について、考えていきます。
<目次>
1. 同一労働同一賃金の原則
1_1. 社員とパート・アルバイトで異なるルールの比較
2. パート・アルバイトでの通勤手当支給とその注意点
2_1. 学生アルバイトの通勤費支給への取り決め
2_2. 非課税限度額の考慮
3. 正確な通勤手当申請の重要性
4. 通勤費管理システムのメリット
5. 最後に
同一労働同一賃金の原則
「同一労働同一賃金」の原則が法律で定められている今、正社員とパート・アルバイトの間で著しく不公平な取扱いがあってはならないとされています。
企業の規定により支給基準はさまざまですが「同一労働同一賃金」の考えのもと、パート・アルバイトにだけ実質的な不利益を与える条件が適用されることは違法となります。一方で、正社員には定期券1か月分を支給し、パートやアルバイトには勤務日数に応じた実費を支給するといった、合理的な違いを設けることは正当な判断となります。
詳しくは厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」をご参照いただくとよいかもしれません。
社員とパート・アルバイトで異なるルールの比較
原則、不公平な取り扱いは行わない前提ですが、社員とパート・アルバイトに対する通勤手当のルールには、厳密には違いが存在します。
正社員には通勤費として前払いでの定期券支給が一般的ですが、パート・アルバイトの場合は、1日の往復費用と勤務日の実績から支給されることも多く、実績に応じた支給とするため支払タイミングが異なるケースもあります。このことから、定期支給と実費での通勤費支給の違いによって実質的な支給額に差が出てくる可能性があります。
「同一労働同一賃金」の考え方によって、通勤手当の基本的な条件はパート・アルバイトであっても正社員と同等の条件を適用するようにはなっていますが、勤務形態による通勤手当の支給額の計算方法の違いは正当です。そのため、労働者間の待遇に差が生じないよう配慮したうえで、合理的な違いについて透明性を保つことは、企業の信頼性向上にもつながります。
通勤手当の規定を公平かつ明確にしておき、会社、従業員双方が納得いくルール整備を行っていくことが大切です。
パート・アルバイトでの通勤手当支給とその注意点
先に述べた通り、パート・アルバイトへの通勤手当支給には、勤務する時間や日数が支給対象に影響を及ぼすこともあります。また、学生アルバイトの場合、定期を利用している場合があり、扱いについて注意が必要です。
学生アルバイトの通勤費支給への取り決め
アルバイトには学生も含まれることでしょう。その場合、勤務地が学生が利用している電車やバスの定期区間内に位置していることもあります。こういったケースに対応するため、定期区間内の通勤費支給の有無については事前に決定しておくことで、通勤手当の支給がスムーズになります。
ただし、通学定期については、発行している交通会社の取り決めにより、通学目的以外の利用を禁じている場合がありますので、しっかりと確認の上、取り決めを定めるようにしていきましょう。
非課税限度額の考慮
パート・アルバイトに通勤手当を支給する時には、非課税限度額について考慮が必要です。
通勤手当の非課税限度額は、通勤手段によって課税金額が異ってきます。公共交通機関を利用した場合は、月15万円までが非課税となり、自家用車やバイクの交通用具を利用した場合は、通勤距離(片道)によって非課税限度額が決定します。
具体的には、自家用車で通勤している場合、片道の通勤距離に応じたガソリン代などで通勤手当が計算され、1か月あたりの合計額が非課税限度額の基準となります。例えば、通勤距離が10キロメートルであれば、車の燃費やガソリン価格を考慮して算出した通勤手当額が、10キロメートルに定められている非課税限度額を超えた部分は、所得税の対象(課税)となります。
公共交通機関と自家用車を併用する場合では、1ヶ月あたりの電車・バス代と車の片道の通勤距離にかかる費用の合計が15万円以内であれば、非課税となります。このように、通勤手段によって、非課税限度額が変動することは、通勤手当を計算するための重要なポイントとなります。
もし、パート・アルバイトで非課税範囲内の収入で就労したいという希望があった場合、通勤手当を支給することによって、その上限を超えた収入となってしまったり、通勤手当自体が非課税限度枠を越してしまうと、所得税が課税されるため、通勤手当を受け取ることを希望しないと考える方もいるかもしれません。しかしながら、通勤手当は公平に支給されるものであること、支給を受け取らないという対応は難しいといった点を踏まえ、通勤手当の非課税限度額についての理解を深めていくことが重要です。
正確な通勤手当申請の重要性
通勤手当を申請する際は、正確性も大切になってきます。一般的に通勤で利用する経路は、会社の規定によって最適な通勤経路が定められるため、経路申請時には、会社の規定に沿った通勤経路・支給額の申請となっているか、確認を行っていくことが求められます。
規定にあった通勤経路を利用しているかを確認するために、申請時には具体的な経路内容の点検や、利用する交通機関の証明を求めるケースもあるでしょう。
また、規定にあっていない通勤経路で利用を続けていたことが発覚した場合、後に返金を求められたり、悪質なケースの場合は懲戒処分を受ける可能性も考えられます。そのため、会社の規定に従った形で通勤経路の申請を行うよう社員に求める必要があります。
後々のトラブルを避けることに繋がりますので、社員へは会社規定の周知徹底をはかり正しい申請を行うことを共有し、そのうえで、申請内容を正確に確認し、規定に反する通勤手当を支給しないよう、確認を行っていくことが大切です。
通勤費管理システムのメリット
通勤費管理システムを導入することには、多くのメリットがあります。
システムを利用することで通勤手当の申請処理の効率化が期待できます。手動での管理やエクセルを使用した計算では、支給漏れや確認ミスが発生しやすいですが、システム化することでこれらのリスクが軽減でき、従業員の通勤費に関する情報を正確かつ迅速に対応することができるようになります。
次に、申請にあがった通勤経路が規定にあっているか確認する場合にもシステム利用は効果的です。従業員が通勤経路を申請する時に、自宅位置と勤務地の位置をもとにシステムが最適となる経路をいくつか提案することで、従業員は自分に適した経路を選ぶことが可能となり、通勤管理業務担当者が経路のチェックを行う処理が不要となります。また、経路の判定はシステム判断となるため、全従業員への公平性を保つことにもつながります。
また、システムが最適経路を判断することで通勤手当も最適化され、企業としての通勤手当コストの平準化が見込まれます。
加えて、正社員の支払ルール、パート・アルバイトの支払ルールを分けて管理したり、勤務日に合わせて実費で支払う通勤手当額の算出も容易に、正確に行うことができます。
通勤費管理システムを導入することは、業務の効率化、コスト削減、データ分析の促進など、多方面にわたるメリットが期待でき、企業の運営にとってもよい選択となるでしょう。
最後に
本記事では、パート・アルバイトにおける通勤手当の重要性やその管理方法について詳しく説明しました。
通勤手当は、パート・アルバイト従業員にとっても経済的な負担を軽減するためのものですが、その支給や管理にはさまざまな考慮が必要です。同一労働同一賃金の原則に基づき、パート・アルバイトと正社員で不合理な待遇差が生じないように配慮することが求められます。また、非課税枠内での就労を希望する従業員への配慮も必要になってきます。
通勤手当を効率的に管理するためには、通勤管理システムを利用することが効率的です。「通勤管理Arvo」では、パート・アルバイトの出勤日をもとに自動で通勤手当を計算したり、本人が出勤日を申請することもできることから、人事・労務担当者の業務負担を大幅に軽減できます。通勤経路の適否判定も可能で、管理作業がスムーズに行えます。
「通勤管理Arvo」にご興味がありましたらお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから
資料ダウンロードはこちらから

